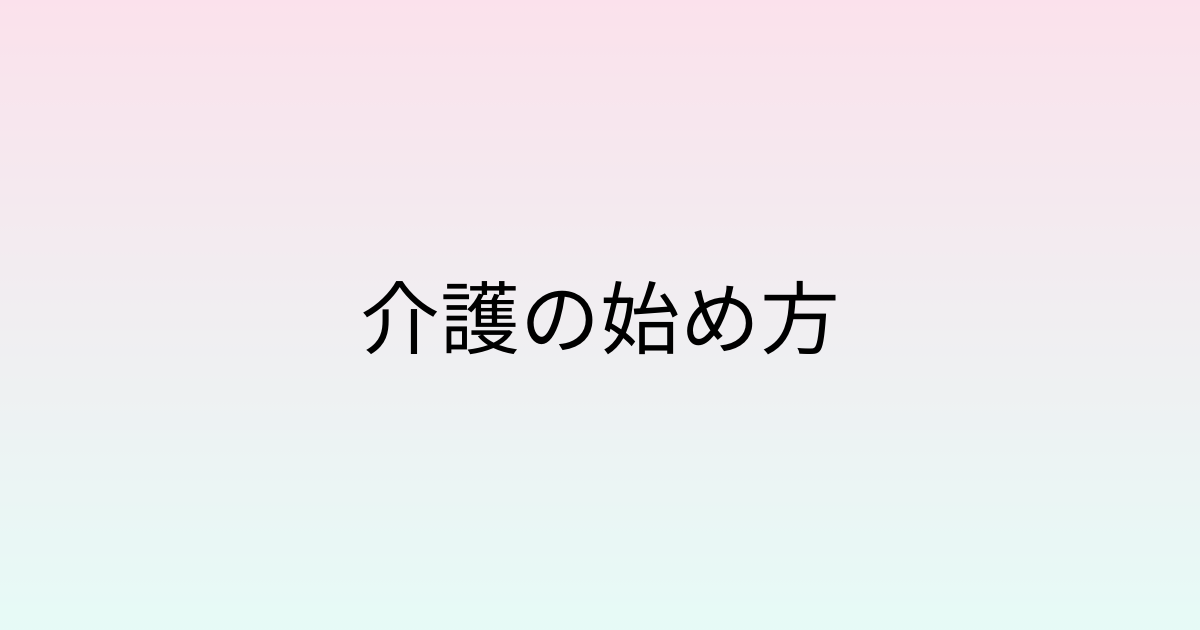
介護の始め方|家族に介護が必要になったら最初にやるべきこと【保存版】
|介護を始める前にやるべきこと
「親が倒れた」「最近ちょっと様子がおかしいかも…」
そんな時、まず頭をよぎるのが“介護って何から始めればいいの?”という疑問を持つ方へ、この記事では「介護の始め方」をやさしく解説します。
実際、介護は突然始まることが多く、事前準備がないまま対応しなければならない状況になりがちです。
そんなとき、真っ先に気になるのが 介護の始め方。この記事では、初めて介護に直面した方に向けて、最初にやるべきことをステップ形式でわかりやすく解説します。
ステップ1|介護の始め方でまず大事な「困っていること」の整理
介護の始まりは、いきなり「介護サービスを使う」ことではありません。
まず大切なのは、今、どんなことで困っているのかを整理することです。
トイレや入浴が不安になってきた
食事の準備ができなくなってきた
外出や通院が難しくなってきた
言動がおかしい、認知症かもしれない
このように、「日常生活のどの部分にサポートが必要か」をはっきりさせると、その後の対応がスムーズになります。
ステップ2|市町村の「介護保険窓口」または「地域包括支援センター」に相談
困りごとが見えてきたら、次は専門機関に相談することが大切です。
相談先としておすすめなのが以下の2つ:
地域包括支援センター(各地域に設置されている介護の相談窓口)
市区町村の介護保険課
どちらも無料で相談でき、要介護認定の申請手続きや、介護サービスの利用方法を案内してくれます。
ステップ3|「要介護認定」を申請しよう
介護サービスを使うには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定の流れ:
市町村の窓口に申請
職員が自宅を訪問し、生活の様子を調査
主治医の意見書を提出
認定審査会で「要介護度」が決定(要支援1〜2/要介護1〜5)
この認定結果に応じて、受けられるサービスの範囲や回数が決まります。
要介護認定とは→厚生労働省:要介護認定
ステップ4|ケアマネジャーと一緒に「ケアプラン」を作成(在宅介護の場合)
要介護認定が出たら、次はケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら、本人の状態に合った「ケアプラン(介護計画)」を立てます。
プランの内容例:
デイサービスに週2回通う
訪問介護で入浴をサポート
配食サービスを利用する など
ケアマネジャーは、介護サービスをコーディネートしてくれる頼れる存在です。困ったことがあれば、まず相談してOK!
👉介護保険サービスの種類と利用できる内容|あなたに合った選び方ガイド
ステップ5|介護サービスを利用開始!費用や利用回数もチェック(在宅介護の場合)
介護サービスの自己負担は原則1割(一定所得以上は2〜3割)です。
たとえば、訪問介護やデイサービスは、1回あたり数百円〜1000円前後の負担で利用可能です。
また、介護度によって月ごとの「支給限度額」が決まっており、その範囲内ならいくつかのサービスを組み合わせて使うことが可能です。
よくある悩みと対処法
■ 親が「介護なんていらない」と拒否してしまう…
無理に説得するよりも、「ちょっとお手伝いしてもらおうか?」と軽く提案するのがおすすめです。ケアマネさんに協力してもらうとスムーズになることも。
■ 認知症っぽいけど、病院に連れていけない
まずはかかりつけ医に相談を。本人が嫌がる場合でも、家族だけで相談できる場合もあります。
■ 兄弟との協力体制がバラバラ…
「何をどう分担するか」を見える化して、LINEグループや共有ノートでのやり取りもおすすめです。
まとめ|介護の始め方に“正解”はない。でも、動き出すことが大切
介護は突然始まることが多く、最初は誰でも戸惑います。
でも、一人で抱え込まず、相談すること・情報を得ることが第一歩です。
「困ったらどこに相談すればいいか」さえ分かっていれば、あとは少しずつ道が開けていきます。
情報を集めて準備することは、将来の自分を助けることにもつながります。
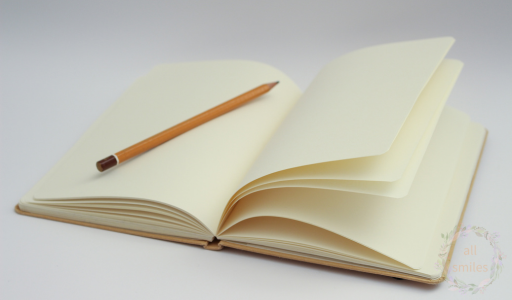
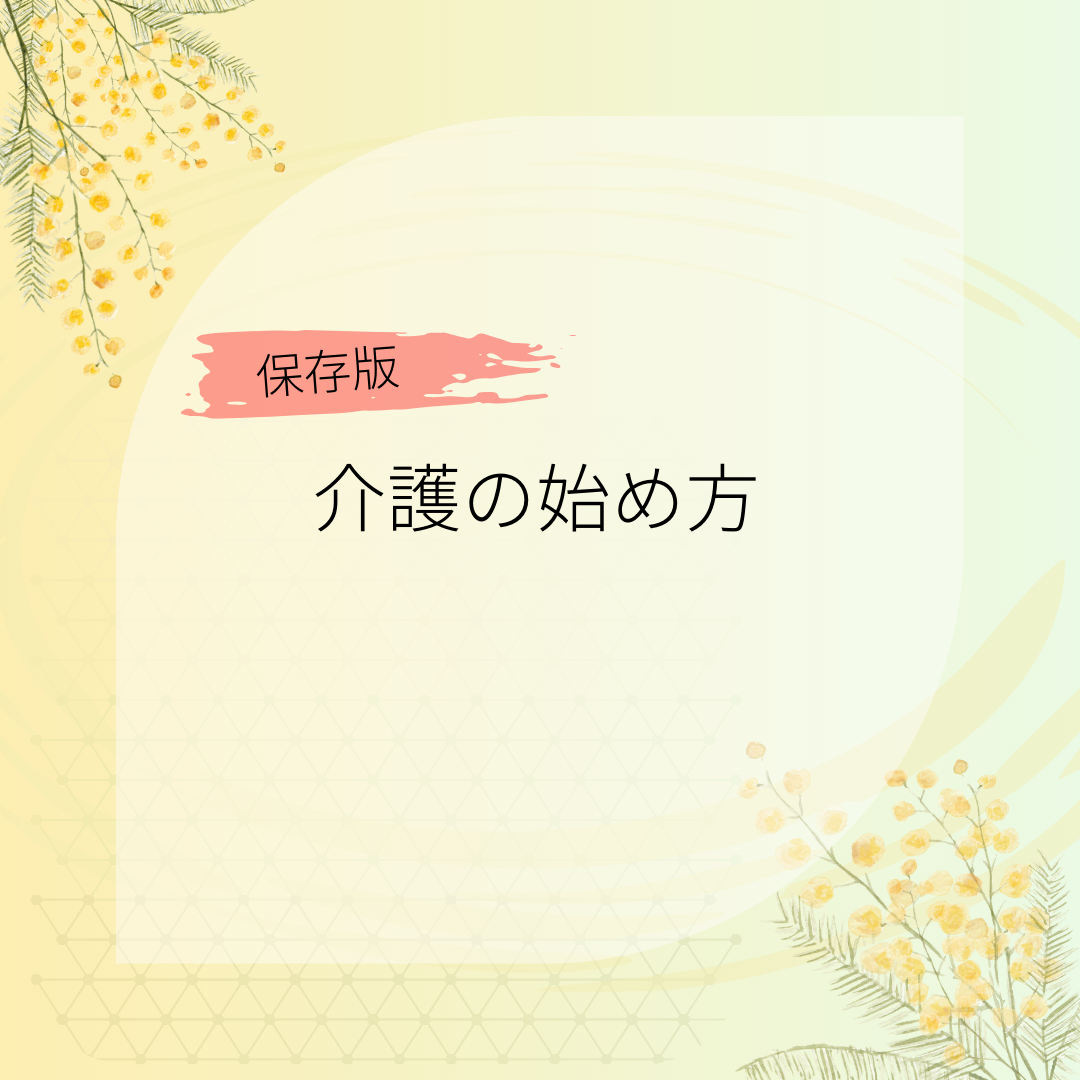
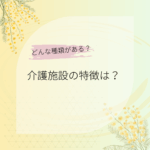
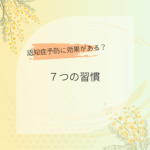
コメント