【初心者向け】親が認知症かも…受診・診断の流れと心の準備まとめ
「最近、親の物忘れが気になる」「同じ話を繰り返すようになった」
そんな小さな違和感に気づいたとき、どう対応すればよいのでしょうか。
この記事では、認知症の可能性に気づいたときの受診・診断の流れと、家族としてできる心の準備をやさしく解説します。
1. 「認知症かも」と思ったら、まず確認したいチェックリスト
加齢による物忘れと、認知症の兆候は似ているようで違います。以下のような変化が増えていませんか?
同じ話を短時間で何度も繰り返す
財布や鍵の置き場所を忘れ、探すことが増えた
慣れた道で迷うようになった
家事や段取りがスムーズにできなくなった
感情の変化(怒りっぽい・頑固・疑い深いなど)
これらが数週間〜数か月続く場合は、受診を検討するサインです。
2. 受診は何科?どこに相談すればいい?
最初の窓口
かかりつけ医(内科)
専門外来(もの忘れ外来)
状況によっては、神経内科・精神科・脳神経内科に紹介されることもあります。
🔍 PR:近くの認知症外来を探すなら「病院なび」がおすすめ
▼ 今すぐチェック:病院なび 認知症外来検索
3. 診断までの流れと、かかる費用
一般的な診断の流れ
問診(本人・家族からの聞き取り)
認知機能検査(MMSEなど)
30問ほどの質問に答える形式。点数で認知機能を測定します。
画像検査(CT・MRI)
脳の萎縮や血流の状態を確認します。
その他の検査(血液検査・心理検査など)
費用の目安(保険適用の場合)
初診料+問診・簡易検査:約3,000〜5,000円
CTやMRI:約5,000〜10,000円
合計:約1〜2万円前後(自己負担1〜3割の場合)
※費用は病院・地域差あり。高額になる場合は医師に事前確認しましょう。
⏱ 診断は1回で終わることもあれば、数回の通院で確定するケースも多いです。
4. 本人が受診を嫌がるときは?
「病院に行きたくない」という抵抗はよくあります。伝え方を工夫するのがポイントです。
| よくある言い分 | おすすめの声かけ |
|---|---|
| 「自分は大丈夫」 | 「年齢的にも健康チェックしよう」 |
| 「病院は嫌だ」 | 「最近ちょっと疲れやすいって言ってたから、相談してみない?」 |
| 「恥ずかしい」 | 「今は早くわかれば進行を遅らせられるんだって」 |
「認知症の検査」ではなく、「健康診断の一部」として提案すると受け入れやすいです。
5. 診断後=すぐに介護ではない
認知症と診断されても、すぐに介護が必要になるわけではありません。
早期診断のメリット
進行を遅らせる治療や生活改善が可能
介護保険や支援制度を段階に応じて利用できる
焦らず、必要な情報を少しずつ整理していきましょう。
📘 関連記事:【保存版】介護の始め方|家族に介護が必要になったら最初にやるべきこと
→ [記事を読む]
6. 家族の心の準備|孤独にならないために
「まさかうちの親が…」と受け入れるには時間がかかるのが普通です。
心の準備に役立つこと
家族内で情報を共有する
1人で抱え込まず、地域包括支援センターに相談
認知症カフェや家族会に参加してみる
地域によってサービス内容や相談先は異なるため、まずは市区町村の窓口に問い合わせると安心です。
まとめ|小さな一歩を踏み出すことから
親の変化に気づいたとき、「見なかったことにしたい」気持ちと「早く対応しなきゃ」という焦りが交錯します。
でも、大切なのはできることを一つずつ。
小さな変化を記録する
無理のない言葉で受診を促す
支援制度や相談窓口を利用する
早期に動くことが、親の暮らしと家族の安心を支える力になります。
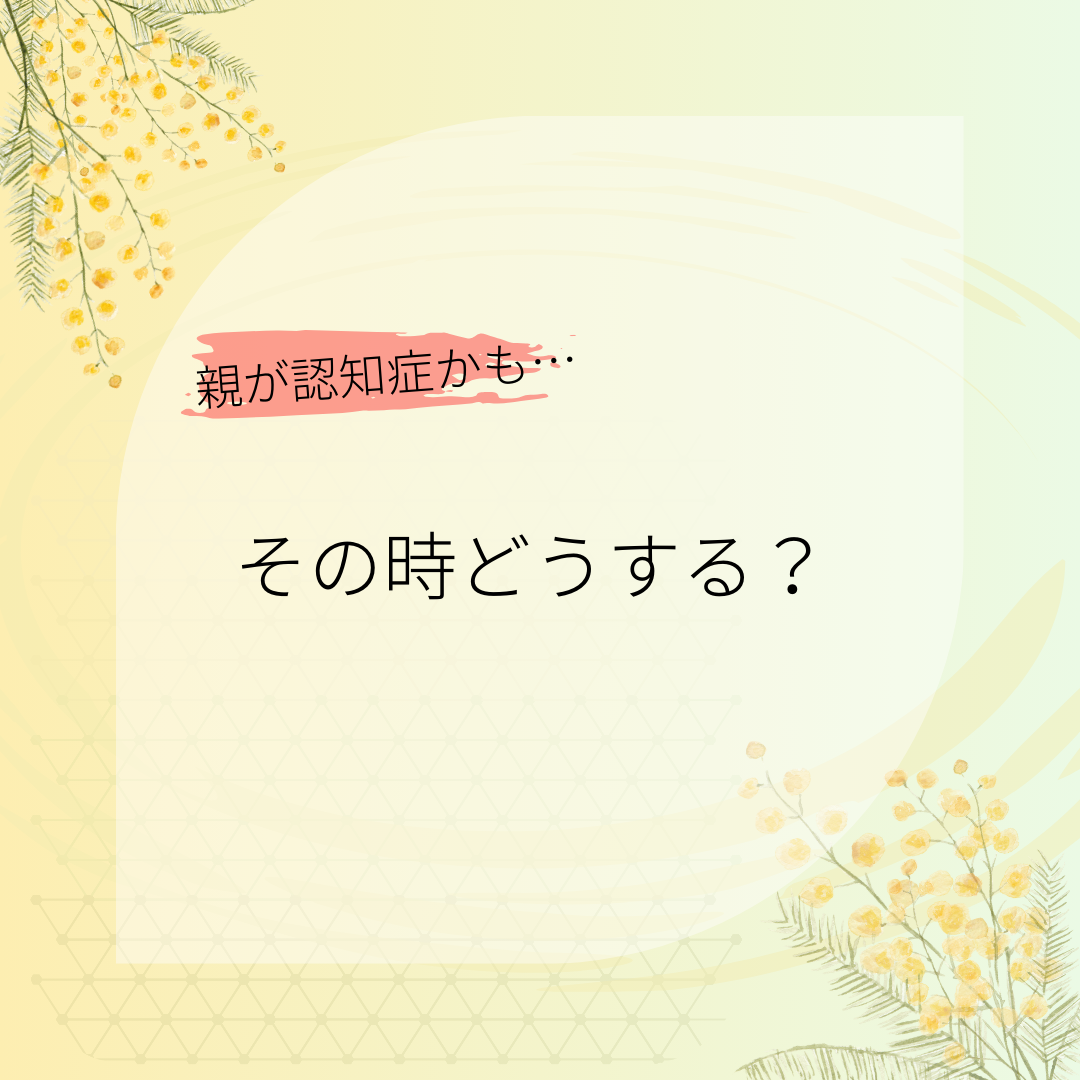
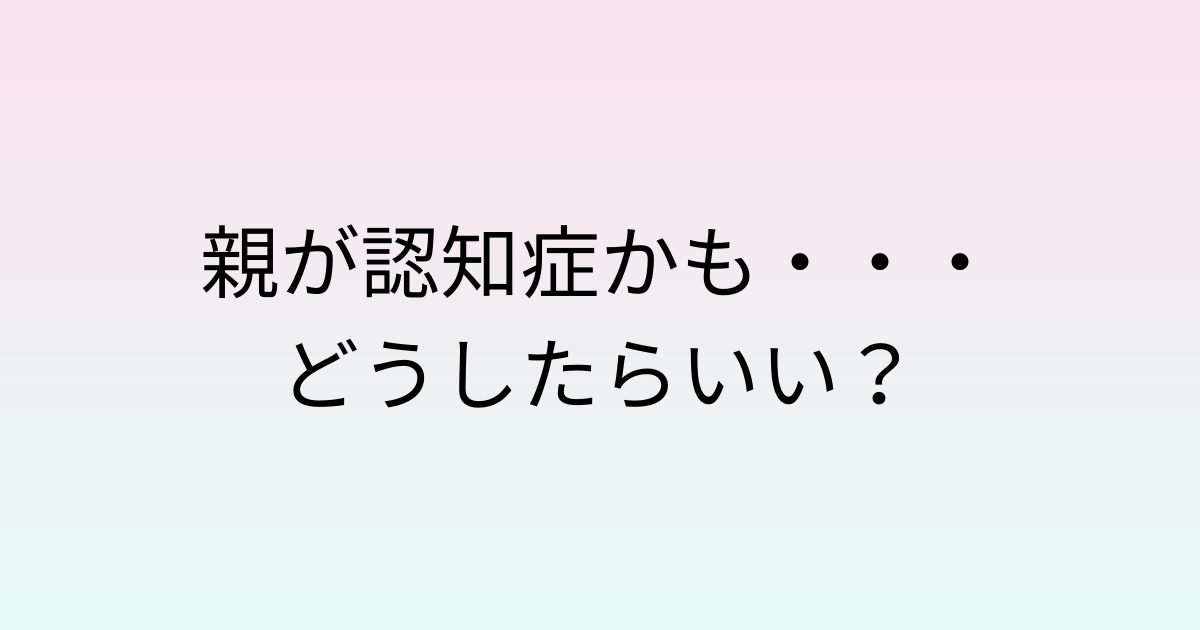
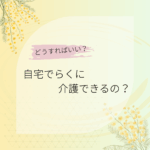
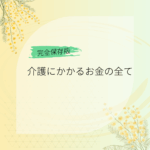
コメント