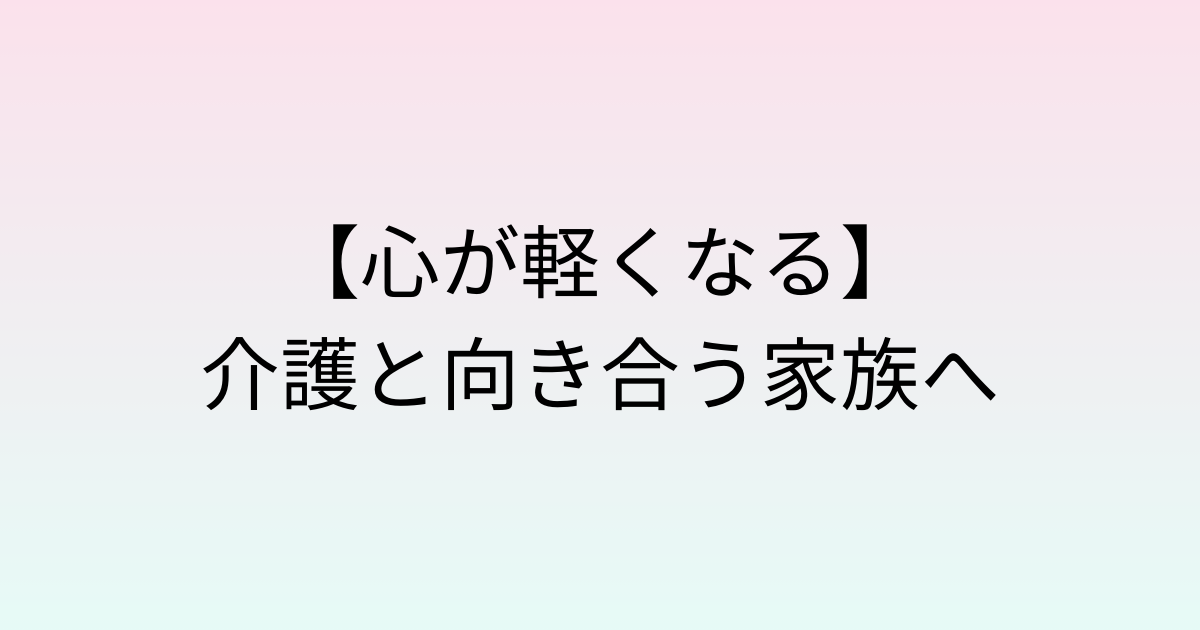
【心が軽くなる】介護と向き合う家族へ|うまく付き合うための5つのヒント
「親の介護をしているけど、ついイライラしてしまう」
「きょうだいと介護の方針でもめてしまった」
「なんで私ばかり…と思ってしまう自分が嫌」
――そんな思いを抱えているのは、あなただけではありません。
介護が始まると、日々の生活の中に感情のゆらぎや家族とのすれ違いが増えていきます。
でも、ちょっとした向き合い方のコツを知っておくだけで、心が少しラクになることもあるんです。
この記事では、家族として認知症や介護とどう向き合えばいいのかを、実践しやすい5つの視点からやさしく解説していきます。
①「感情の波」はあって当たり前|自分を責めないこと
介護中は、どうしても怒り・悲しみ・罪悪感・不安など、たくさんの感情がわいてきます。
「つい怒ってしまった」
「もっとやさしく接すればよかった…」
と自分を責める人も多いですが、完璧な介護なんてありません。
🌿ワンポイント
感情がゆれるのは“それだけ真剣に向き合っている証”
無理にポジティブになろうとせず、気持ちをノートに書いてみるのもおすすめ
まずは、“自分をいたわること”が家族介護の第一歩です。
②「1人で抱えない」ための環境づくりを
介護はチーム戦。家族だけで完結させる必要はありません。
🧩頼っていい存在
ケアマネジャー・介護サービス事業所
地域包括支援センター(相談窓口)
介護経験者の集まり・オンラインコミュニティ
家族が多くても「結局ひとりでやってる…」という状況はよくあります。
だからこそ、第三者の視点を入れることで“気づき”が生まれることもあるんです。
③ きょうだいとの「温度差」は当たり前|役割のバランスを
きょうだいがいる場合、介護の温度差や負担の不公平さがストレスのもとになります。
「私は毎日お世話してるのに、あの人は何もしてくれない」
「金銭面だけで済まそうとしてる」
…と不満がつのる前に、“できることを分担する”話し合いが必要です。
🤝分担のアイデア
金銭面→援助してもらう
手続き・通院→離れて暮らすきょうだいが担当
感情面のサポート→LINEで相談に乗ってもらう
「同じことをしなくてもいい」
「それぞれの立場でできることをする」
という視点が、お互いの関係を守るカギになります。
④ 親との関係を“再構築”する気持ちで向き合う
認知症が進むと、これまでの親とは違う一面を見ることもあります。
時に悲しみや混乱を覚えるかもしれません。
でも、「できなくなったこと」ばかりを見るより、今の親とどう関わるかに目を向けてみてください。
☺️関わり方のヒント
懐かしい音楽や写真を使って一緒に思い出をたどる
「できること」に目を向け、やってもらう機会をつくる
介護=お世話ではなく「一緒に過ごす時間」として考える
“昔の親”ではなく、“今ここにいる親”と新たな関係を築いていく感覚が大切です。
⑤ 家族にも「休息」と「笑い」を忘れない
介護には終わりが見えにくいことも多く、気づけば自分自身を見失ってしまうこともあります。
だからこそ、「ちょっと手を抜く」「笑う時間を持つ」ことは、介護を続けるための大事なエネルギーです。
💤こんなことから始めてみよう
週に1日はショートステイやデイサービスを活用して「休みの日」をつくる
同じ立場の人とおしゃべりをする(介護カフェなど)
推し活・ピラティス・好きなスイーツなど、自分時間を確保
介護者が笑顔になれる時間があると、家庭全体の空気もやわらかくなるんです。
まとめ|「家族だからこそ、うまくいかない」が普通なんです
介護と向き合う中で、
「なんでうちだけこんなに大変なんだろう」
「もっと良い家族でいたかった」
そう思ってしまう瞬間があるかもしれません。
でも、それはあなただけではありません。
家族との関係は、
✔すれ違ってもいい
✔本音を出していい
✔誰かに頼っていい
――そうやって、“完璧じゃない関係”を受け入れていくことが、いちばん大切な向き合い方です。
あなたの毎日が、少しでも軽くなりますように。
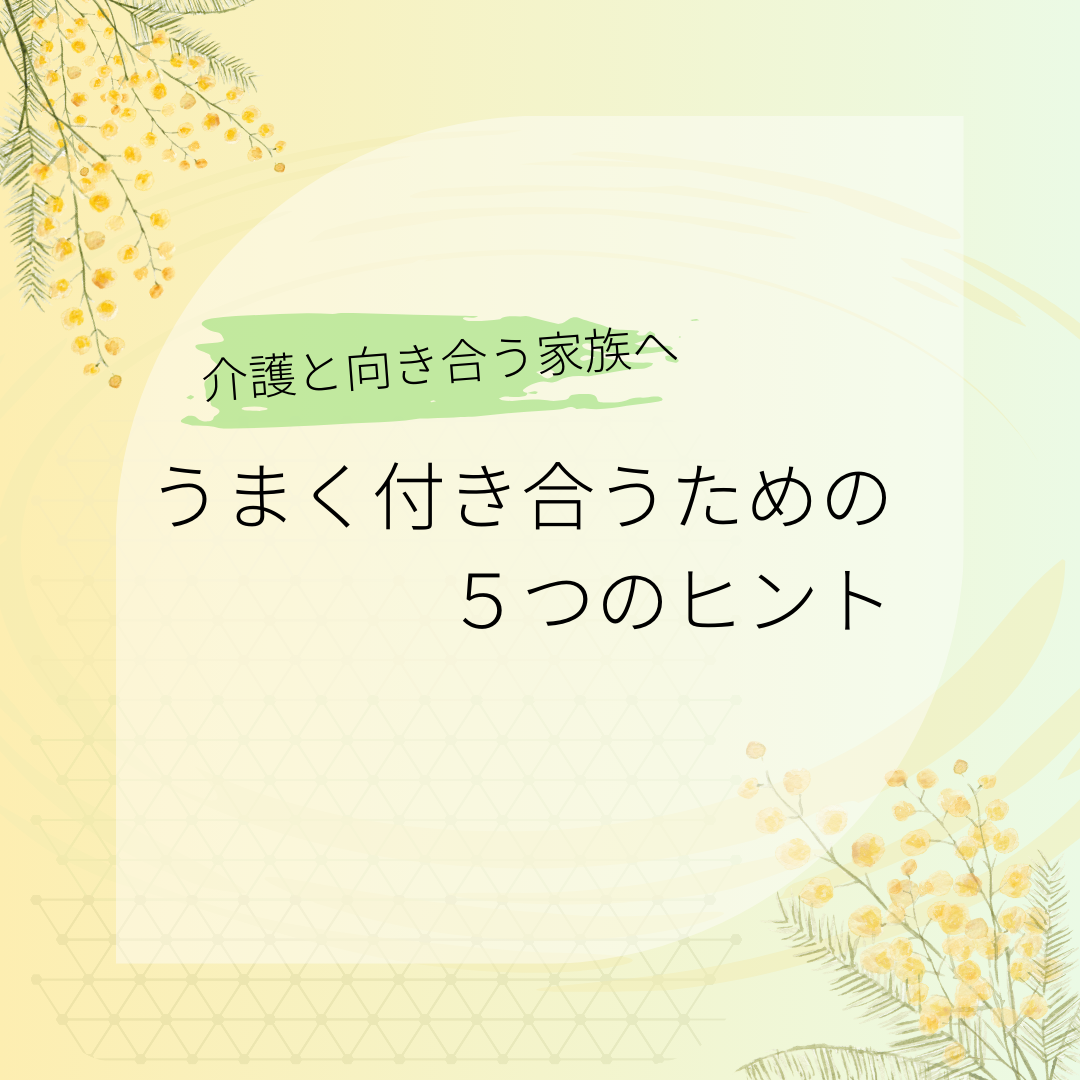
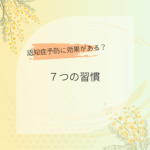
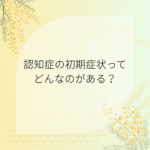
コメント