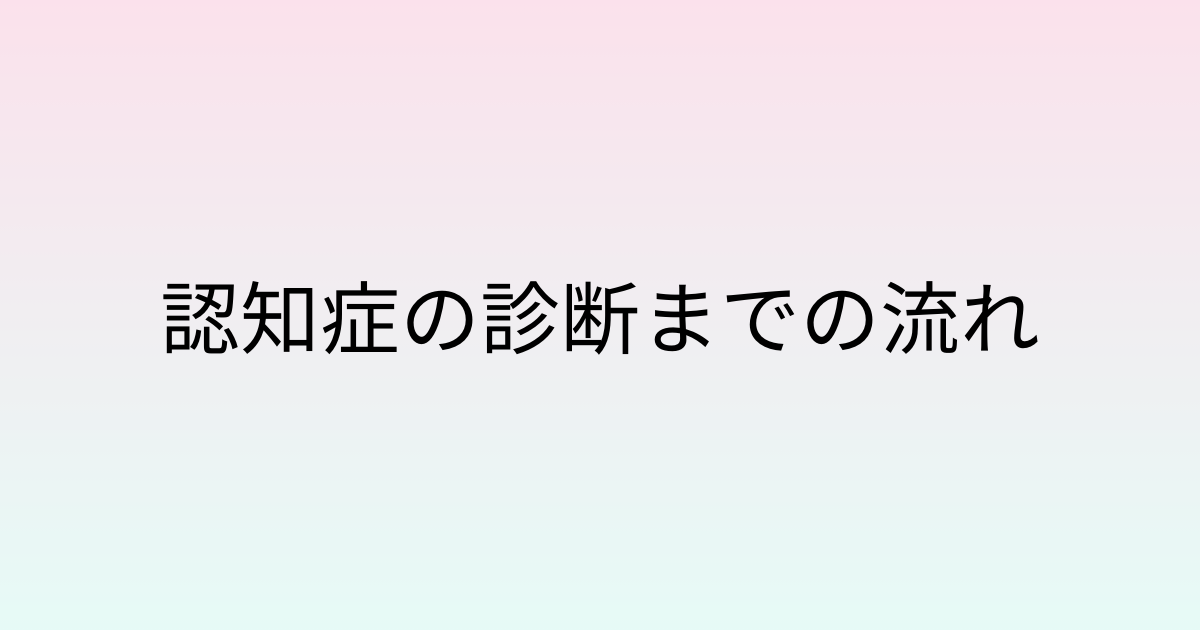
【初心者向け】認知症の診断までの流れ|不安な気持ちに寄り添う5つのステップ
「もしかして認知症…?」
親のちょっとした変化に気づいたとき、あなたが最初にとるべき行動とは?
- どこに相談したらいいの?
- 病院で何をするの?
- 認知症だったらどうなるの?
そんな不安を抱えるご家族向けに、認知症の診断までの流れを5つのステップでわかりやすく解説します。あわせて、相談窓口や受診時のチェックリストも紹介します。
ステップ1|小さな変化に気づくことが最初の一歩
認知症の初期サインはとてもさりげなく、こんな行動が増えてきたら注意が必要です。
✅ 財布や鍵をよく探す
✅ 昨日話したことをまた聞いてくる
✅ 食事や掃除に無関心になってきた
「あれ?」と思ったら、スマホやノートにメモしておくのがおすすめ。
受診時に医師へ伝える材料になります。
👉【やさしく解説】認知症の種類と特徴|知っておきたい4つのタイプ
ステップ2|まずは相談。地域包括支援センターへ
「病院に行くのはちょっと早いかも…」
そんなときは、無料で相談できる窓口からはじめましょう。
📌 相談先一覧
- 地域包括支援センター(お住まいの市町村に必ずあります)
- かかりつけ医
- 認知症疾患医療センター(専門性が高い)
「こんな感じなんですが、受診すべきですか?」と相談するだけでもOK。
ステップ3|病院での問診と簡単なテスト
受診すると、まず医師が丁寧に話を聞いてくれます。
受診時に聞かれること
- 気になり始めた時期
- どんな行動に困っているか
- 家族のサポート状況や生活環境
その後、簡単な記憶力テスト(MMSEなど)が行われます。
本人と家族、両方の話を聞くことが診断の鍵になります。
ステップ4|必要に応じた検査(数日〜1週間程度)
問診で認知症が疑われた場合は、以下のような検査が行われます。
| 検査の種類 | 内容 |
|---|---|
| 血液検査 | 他の病気との見分け(甲状腺異常、ビタミン不足など) |
| CT/MRI | 脳の萎縮・血流を見る画像検査 |
| 心理検査 | 記憶・注意力・理解力のチェック |
⚠️ 検査の一部は専門病院を紹介されることもあります。
ステップ5|診断とこれからの説明
検査の結果をふまえ、医師から以下の説明があります。
- 現時点で認知症かどうか
- 今後の進行や注意点
- 介護サービスの案内や相談窓口
認知症と診断されても、すぐにすべてを支えなければいけないわけではありません。
「これからの準備」が早めにできることが、家族の安心につながります。
よくある質問(Q&A)
Q. 本人が受診を嫌がったらどうする?
A. 「健康診断のついでに行こうか」など、やんわり誘うのがコツ。“心配してるよ”という気持ちを伝えるだけでも違います。
Q. もし認知症じゃなかったら?
A. うつ病やストレス、一時的な薬の副作用が原因のことも。診断を受けることで安心につながるので、早めの受診を。
まとめ|“大げさかも”と悩むあなたが、一番大切な変化に気づいています
「病院に行くほどじゃないかも…」と思っても、あなたの気づきこそが早期発見のカギ。
認知症の診断は“終わり”ではなく、生活を整えるためのスタートライン。
焦らず、少しずつ進めていきましょう。
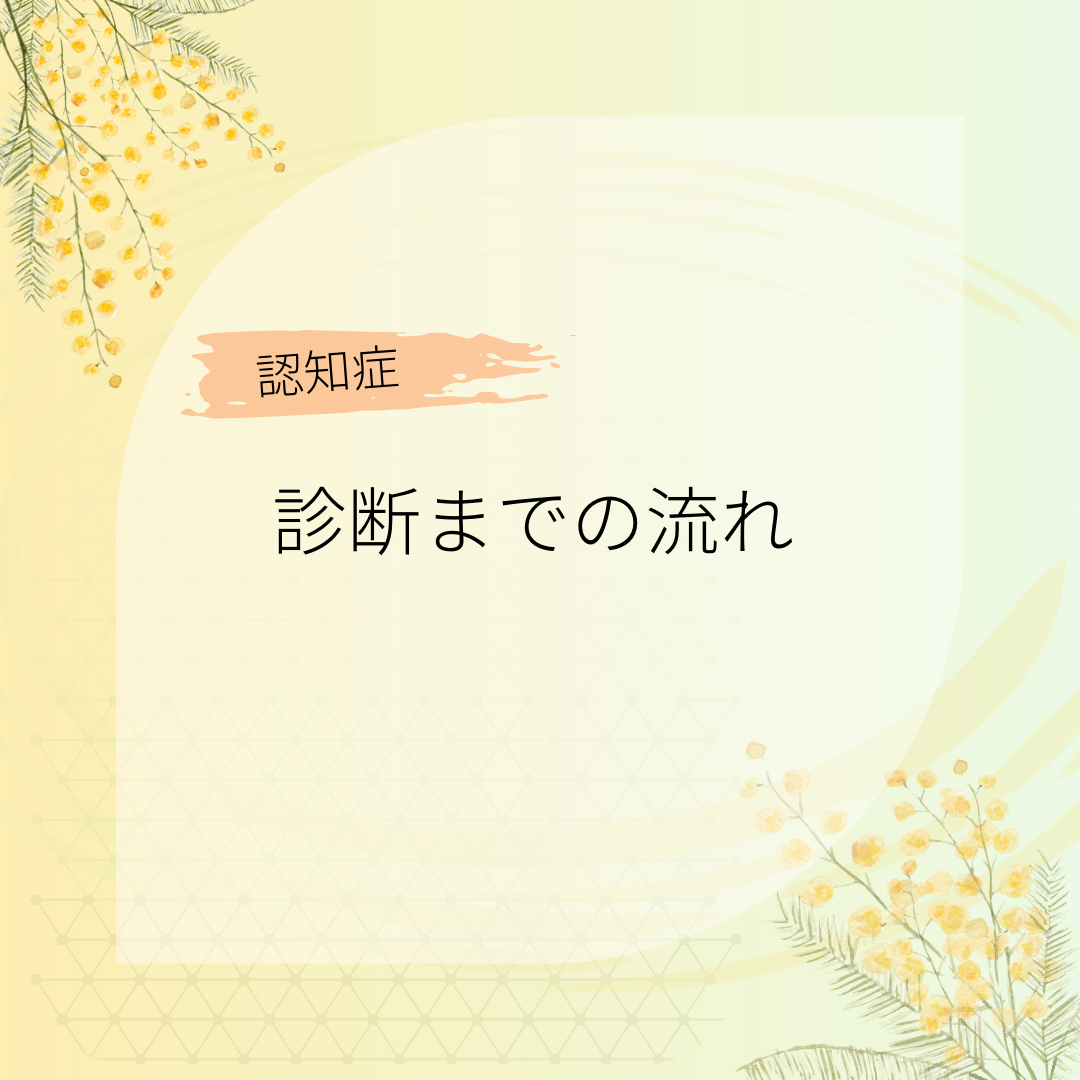
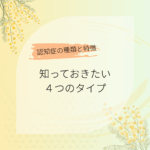
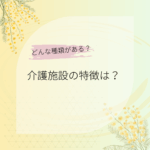
コメント