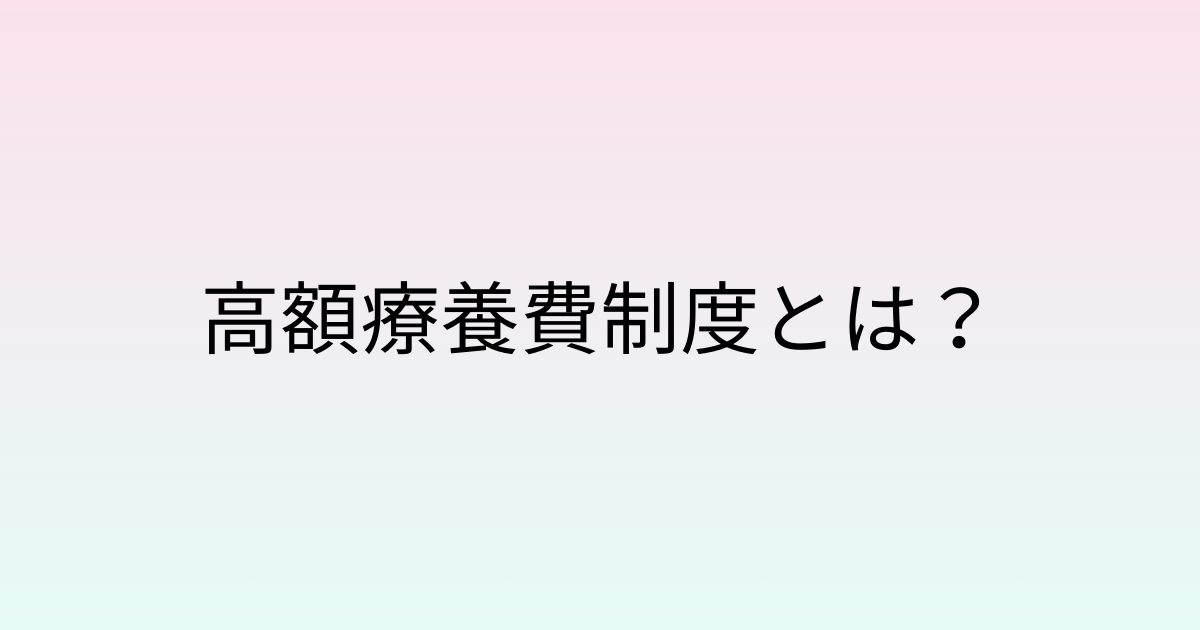
高額療養費制度とは?知らないと損する医療費の仕組み【2025年版】
今回は『介護』ではなく、『医療』をテーマにしています。
どちらも必要なものですが、同時に使うことはほぼできません。施設入所中の方が医療機関を受診する場合は、必ず施設の方に支払いについて確認することをおすすめします。
ちなみに『介護』で支払いは高額になった場合は”高額介護サービス費”というものがあります。それはまた別の記事でご紹介します。
「医療費が高すぎる…」そんなときに頼れる国の制度
急な入院や手術で「えっ、こんなにかかるの⁉」と不安になった経験、ありませんか?
実は、医療費が高額になったとき、一定額以上は払い戻してくれる公的制度があります。それが【高額療養費制度】
ですが、この制度を知らなかったばかりに、何万円も損してしまう人も少なくないんです。
この記事では、最新の情報(マイナカード対応も含む)をもとに、申請方法や注意点までわかりやすく解説します。
高額療養費制度とは?|医療費が高額でも家計を守れる仕組み
高額療養費制度とは、月ごとの医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超過分があとから戻ってくる制度。対象は公的医療保険に加入しているすべての人です。
つまり、
- 高額な入院や治療を受けても、
- 自分の収入に応じた上限を払えばOK。
- 残りは払い戻される or 最初から支払わずに済む
という、家計の味方のような制度です。
年収別|自己負担限度額の目安(70歳未満)
| 区分 | 年収目安 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| ア | 約1,160万円〜 | 約252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| イ | 約770〜1,160万円 | 約167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| ウ | 約370〜770万円 | 約80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| エ | ~約370万円 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※70歳以上の方は別の基準があります。
【重要】マイナンバーカードがあると申請不要に!
従来は「限度額適用認定証」を取得して病院に提示しないと、医療費は全額立て替え→後日申請、という流れでした。
ですが、2021年以降、マイナンバーカードを保険証として登録していれば、申請不要で限度額が自動適用されます!
◆この機能があると…
- 窓口での支払いが最初から自己負担限度額まででOK
- 認定証の申請・持参の手間なし
- 急な入院時でも慌てない
◆利用するには?
- マイナポータルまたはコンビニの端末などで「保険証利用の申込」をするだけ
- 対応している医療機関で自動的に限度額が反映
それでも申請が必要なケースは?
マイナンバーカードを使っていない or 病院が非対応の場合は、事後に高額療養費の申請が必要です。
【申請の流れ】
- 医療機関で全額(3割負担)を支払う
- 後日、健康保険組合 or 国保窓口に申請
- 約2〜3か月後、口座に返金
知らなきゃ損する注意点3つ
① 月をまたぐと別計算になる
医療費の計算は「1か月単位(1日〜末日)」でリセットされます。月をまたいだ入院は合算できず、返金額が少なくなることも。
② 保険適用外は対象外
差額ベッド代や食事代、先進医療などは対象外。これらには別の備えが必要です。
③ 家族の医療費は「世帯合算」が可能
同じ保険に加入していれば、複数人分の医療費をまとめて限度額に反映できます。家族で入院が重なった月などに活用を。
実際どう?体験談|マイナカードで支払いがスムーズに!
Sakiさんの読者層に近い、50代女性の事例です。
急な腹痛で親が入院。高額療養費のことは知っていたけど、何も準備していなかったそう。しかし、マイナンバーカードを保険証登録していたおかげで、病院での支払いはその場で57,600円までに抑えられたとのこと。
「何もしなかったのに自動で限度額が反映されたのは驚きでした」との声も。
高額療養費+医療保険で安心はさらにアップ!
高額療養費制度は治療費の基本部分をカバーするものですが、差額ベッド代や通院費、収入減などは自己負担。そこでおすすめなのが、医療保険や先進医療特約での補完。
まとめ|マイナカードと高額療養費制度で「安心の医療費対策」を
高額療養費制度は、使い方を知っているだけで何万円もの医療費負担を軽くできる制度です。
特に、マイナンバーカードの保険証利用登録をしておけば、申請不要で限度額が反映されるため、備えておいて損はありません。
「親がいつ病気になるか不安…」という方は、今この瞬間からできる対策として、
- マイナンバーカードの保険証登録
- 世帯の医療保険の見直しをチェックしてみてくださいね。
追記:マイナンバーカード健康保険証利用の見直しについて
現在、高額療養費制度の利用において、マイナンバーカードを健康保険証として登録していれば、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられ、申請も不要となっています。
ただし、この”「マイナ保険証」制度については、今後見直し・廃止が予定されている”という報道もあり、制度の変更が検討されています。
現時点ではまだ利用可能ですが、制度改正の動きには今後も注目しておく必要があります。
ブログでも最新情報が出次第、随時アップデートしていきますので、必要な方はブックマークしてご活用くださいね。
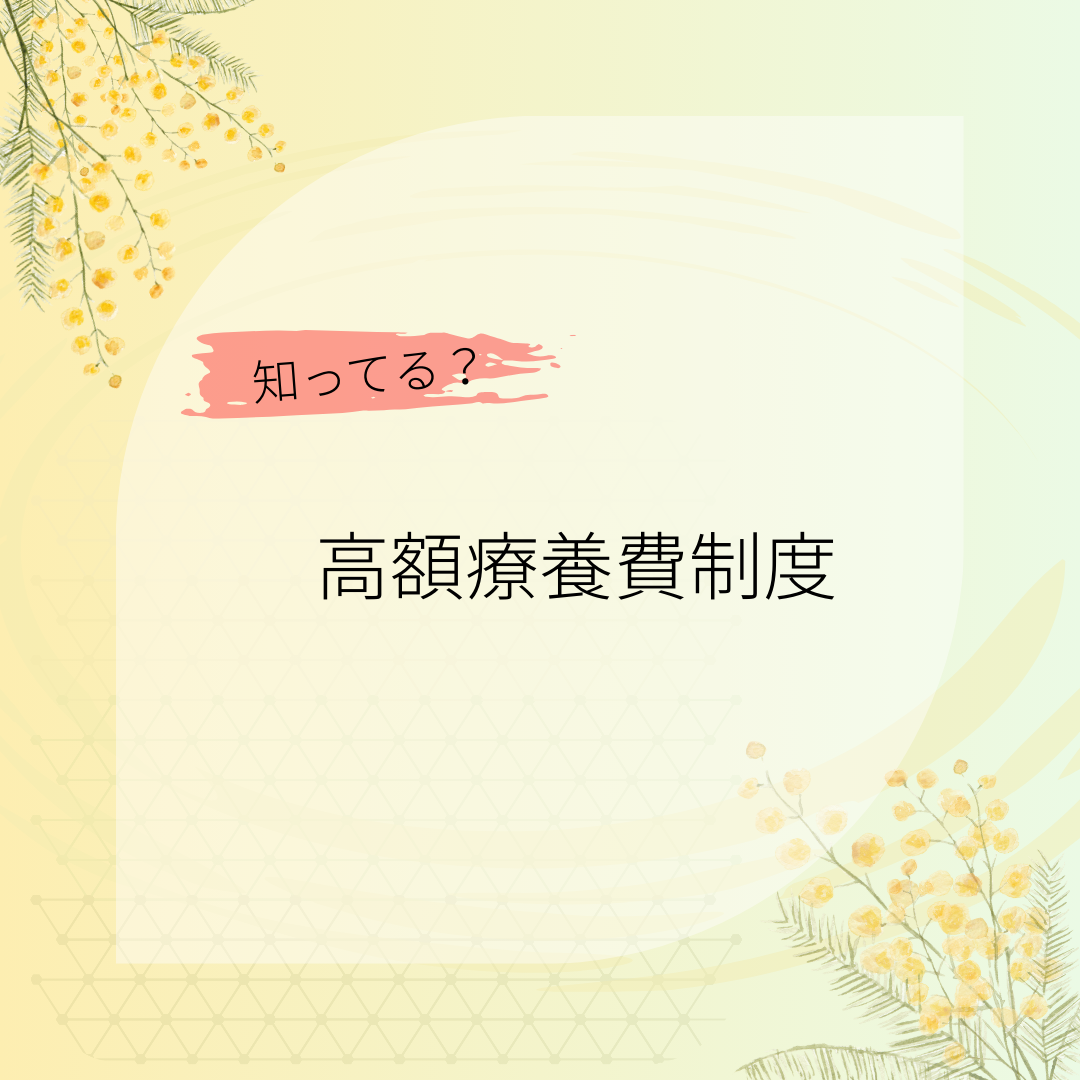
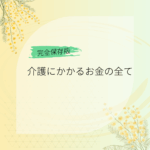
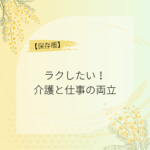
コメント