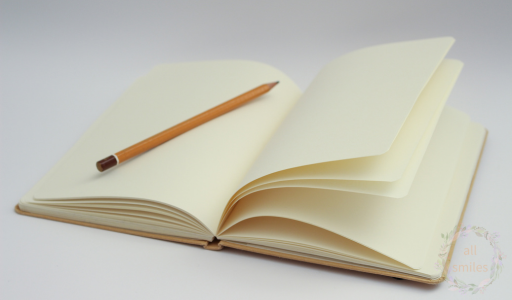
【初心者向け】介護保険とは?対象者・サービス内容・利用手順をやさしく解説
「親が高齢になってきたけど、何から準備すればいいの?」
「介護保険って聞いたことはあるけど、仕組みがよくわからない…」
そんな不安を感じている方に向けて、この記事では介護保険の基本をわかりやすく解説します。
- 誰が使える制度なのか
- どんなサービスが受けられるのか
- 利用までの流れや費用の目安
介護は“突然やってくる”ことが多いもの。
「まだ先」と思わず、まずは制度を知ることがあなたと家族を守る第一歩です。
介護保険とは?|家族の介護を支える公的制度
介護保険は、介護が必要になったときに費用の一部を公的にカバーしてくれる制度です。
- 2000年スタート
- 自己負担は原則1〜3割
- 「家族まかせ」から「社会全体で支える」仕組みへ
訪問介護やデイサービスなど、自宅でも施設でも使えるサービスが充実しています。
誰が使えるの?|40歳以上の人が対象
第1号被保険者(65歳以上)
介護が必要と認定されれば、原因を問わずサービス利用OK。
第2号被保険者(40〜64歳)
医療保険加入者で、特定の病気(※)が原因で介護が必要な場合に対象。
※ 若年性認知症、脳血管疾患、パーキンソン病などの16疾病
どんなサービスが受けられる?|主な介護保険サービス
在宅で利用できるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ):家事や入浴などをサポート
- デイサービス:施設に通い、食事・入浴・レクリエーションを受ける
- 訪問看護:看護師が健康管理や医療的ケアを提供
施設でのサービス
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- グループホーム(認知症対応)
👉 施設によって条件や費用が異なるため、見学や事前相談が大切です。
どうやって使うの?|介護保険の申請から利用まで
- 市区町村の窓口で要介護認定を申請
- 訪問調査(職員が自宅訪問)
- 主治医の意見書の提出
- 介護認定審査会で審査
- 要支援・要介護の度合いが決定
認定後はケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用開始となります。
費用はどのくらい?|自己負担の目安と上限
原則、サービス利用料の**1割(所得により2~3割)**を負担します。
| サービス | 自己負担の目安 |
|---|---|
| 訪問介護(30分) | 約250円〜 |
| デイサービス(1日) | 約500〜1,000円程度 |
⚠ 利用には「月ごとの支給限度額」があり、上限を超えると全額自己負担になります。
→ ケアマネジャーと相談しながら利用調整をしましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 認知症の親でも使える?
→ はい、認知症も介護保険の対象です。認定を受ければサービス利用できます。
Q. 一度申請したらずっと使える?
→ 要介護認定には有効期限(6〜12ヶ月)があり、定期的に更新があります。
Q. どこに相談すればいい?
→ 市町村の介護保険課、または地域包括支援センターが相談窓口です。
まとめ|「制度を知ること」が安心の第一歩
介護保険を知っておけば、
✔ 突然の介護に慌てない
✔ 自分や家族を守れる選択肢が広がる
まだ介護が始まっていない方こそ、今のうちに制度を把握しておくことが大切です。
関連記事もチェック
👉介護保険サービスの種類と利用できる内容|あなたに合った選び方ガイド
こちらもおすすめ
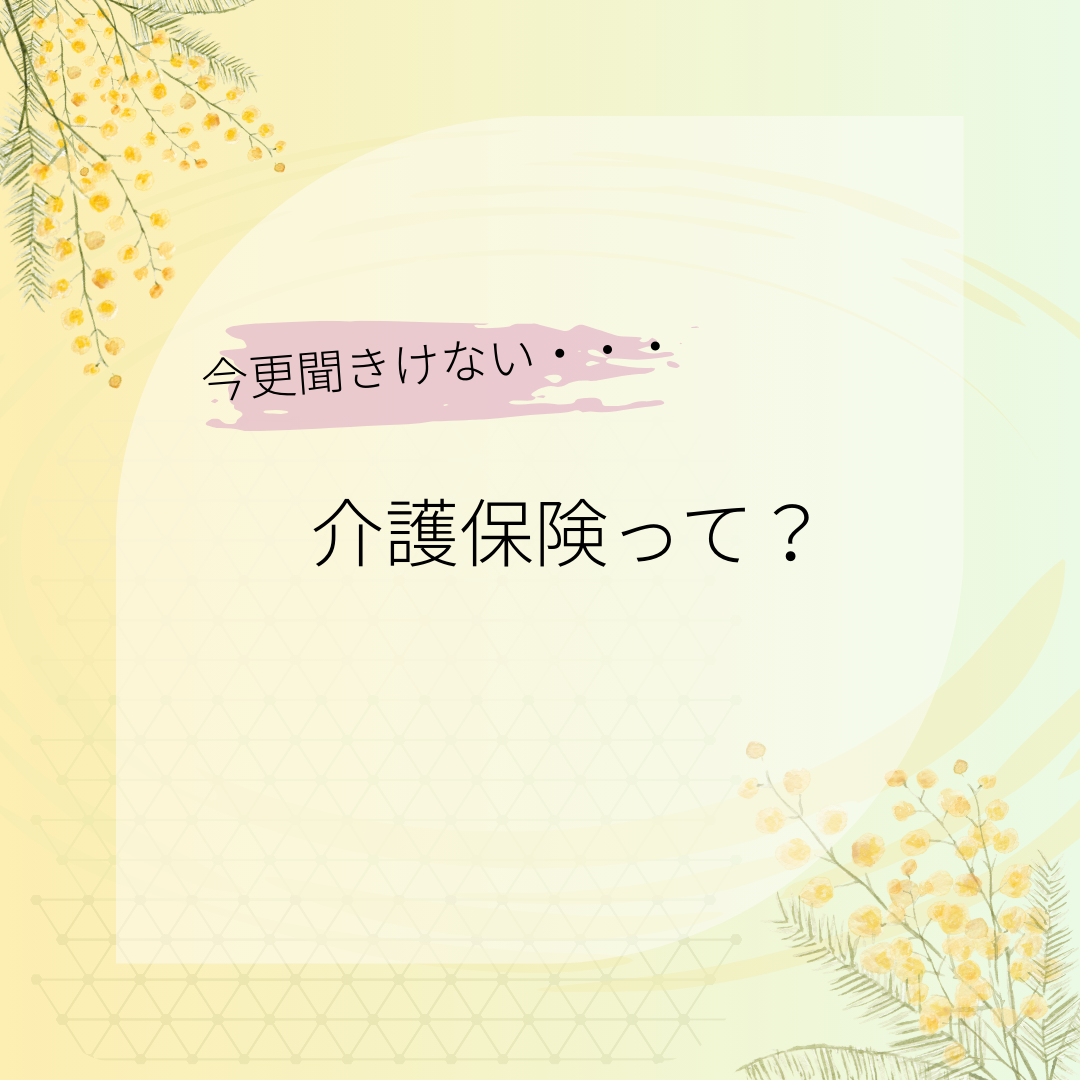
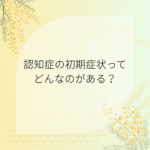
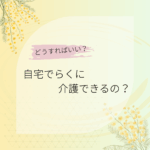
コメント