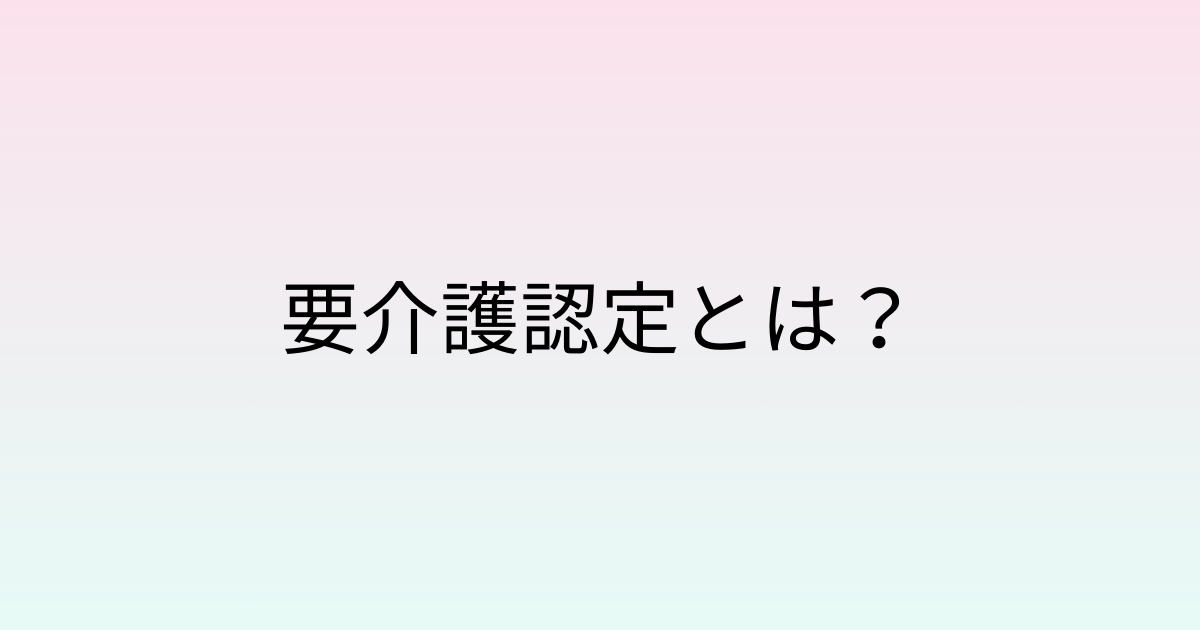
要介護認定とは?申請方法や流れをやさしく解説【家族が介護を必要としたら】
「親が転倒して入院。退院後もこのまま家で生活できるのか心配…」
そんなとき、まず知っておきたいのが「要介護認定」の制度です。
この認定を受けることで、介護保険サービスを利用できるようになります。
本記事では、
- 要介護認定とは何か
- 申請方法と流れ
- 認定の種類と違い
- よくある疑問
などを、初心者にもわかりやすく解説します。
要介護認定とは?
要介護認定とは、介護保険制度にもとづき、自治体が「どの程度の介護が必要か」を判断する制度です。
認定されることで、デイサービスや訪問介護、福祉用具レンタルなどの介護保険サービスを自己負担1〜3割で利用できるようになります。
つまり、「いま、どれだけサポートが必要なのか」を明確にし、適切なサービスを使えるようにするためのスタートラインなのです。
要介護認定の申請方法と流れ
1. 申請の窓口は「市区町村の介護保険課」
まずは、本人または家族が自治体に申請します。
相談や代行は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所でも可能です。
2. 訪問調査
市区町村から委託を受けた調査員(主に看護師など)が自宅などを訪問し、本人の状態をチェックします。
チェック内容は、歩行や食事、排泄、認知機能など74項目以上にわたります。
3. 主治医の意見書
本人のかかりつけ医に、医学的な視点での「意見書」を作成してもらいます。
4. コンピュータ判定+審査会
訪問調査の内容をもとに一次判定(コンピュータによる分析)が行われ、その後、専門家(医師・保健師・ケアマネなど)で構成される「介護認定審査会」によって最終判定が下されます。
5. 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、郵送で結果が届きます。
要支援と要介護の違いは?
認定結果には、以下の7段階があります:
| 認定区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 軽度の支援があれば自立可能 |
| 要支援2 | 一部に介助が必要 |
| 要介護1 | 軽い介護が必要 |
| 要介護2 | 部分的な介助がより必要 |
| 要介護3 | 日常生活の多くに介助が必要 |
| 要介護4 | ほぼ全面的な介護が必要 |
| 要介護5 | 常時の介護が必要な状態 |
ポイントは、要支援1〜2は「自立支援中心」、要介護1〜5は「介護中心」のサービスが利用できるという違いです。
認定を受けると使えるサービス例
- デイサービス(通所介護)
- ホームヘルプ(訪問介護)
- ショートステイ(短期入所)
- 福祉用具のレンタル・購入
- 住宅改修(手すり・段差解消など)
- ケアマネジャーによるケアプラン作成
サービスの内容や回数は、認定された介護度の限度額に応じて決まります。ただし、介護保険外の(実費)の利用で限度額を超えて利用することも可能です。
よくある質問
Q. 要介護認定の有効期限は?
初回は原則6か月間、2回目以降は状態に応じて12〜24か月の期間が設定されます。
Q. 認定に不服があるときは?
市町村に「異議申し立て」が可能です。また、再申請(更新や区分変更)もできます。
Q. 認定されなかったらどうすれば?
「非該当(自立)」とされた場合でも、地域包括支援センターに相談すれば、介護予防や地域支援事業を紹介してもらえることがあります。
まとめ|要介護認定は、介護の第一歩
家族の介護が必要になったとき、
「どこに相談すればいいかわからない」「まず何をすればいいの?」
と不安になりますよね。
要介護認定の申請は、そんな不安を軽くし、制度を使って介護負担を軽減する第一歩です。
相談や手続きに迷ったら、地域包括支援センターに気軽に相談してみましょう。
Sakiブログでは、これから介護が始まる方に向けて、わかりやすく安心できる情報を発信しています。
次回は「ケアプランって何?どう作るの?」についてもお届け予定です。
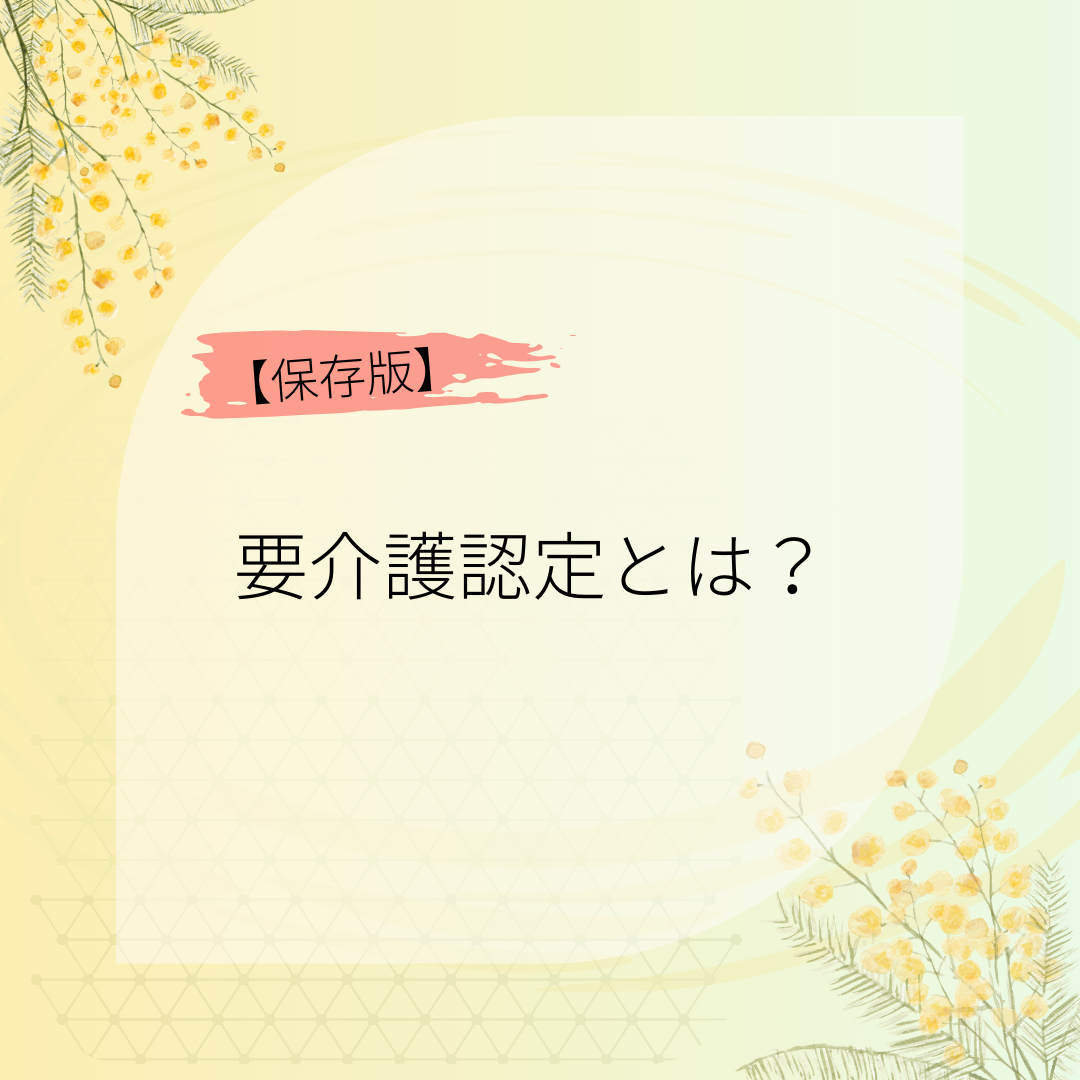
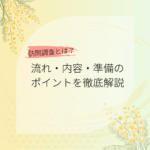
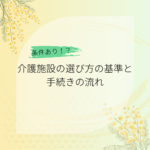
コメント