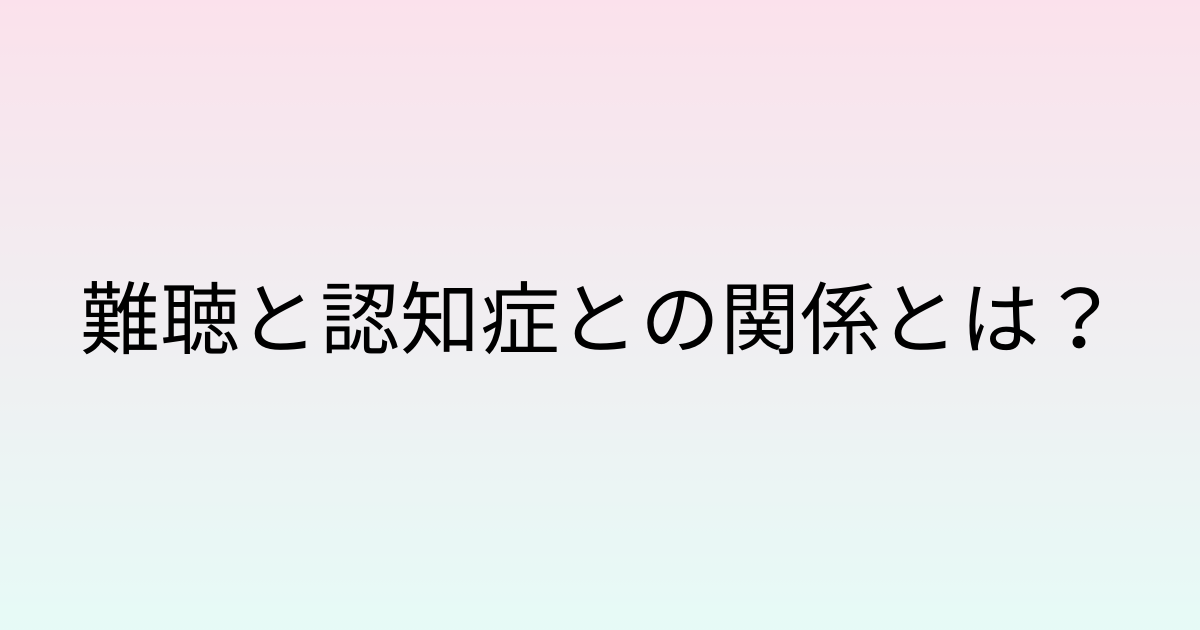
難聴と認知症の関係|脳への影響と早期対策をわかりやすく解説
最近、「難聴が認知症のリスクを高める」という情報を耳にすることが増えてきました。この記事では、難聴と認知症の関係に注目し、なぜ聞こえの問題が脳の健康に影響するのかをわかりやすく解説します。また、日常生活で取り入れられる予防法についてもご紹介します。
難聴と認知症の関係を理解しよう
1. 難聴がもたらす脳への影響
加齢性難聴は、ただ聞こえづらくなるだけではありません。音を処理する脳の領域が刺激を受けにくくなり、脳の活動が低下することがわかっています。難聴と認知症の関係は、このような脳の活動低下と深く結びついています。長期間続くと、認知機能全体の衰えにつながるリスクがあります。
2. コミュニケーション不足が社会的孤立に
聞こえが悪くなると、会話が億劫になり、外出を控えるようになります。これにより、孤立やうつ状態になりやすくなり、それがさらに認知機能の低下を招くという悪循環に陥ることも。難聴と認知症の関係は、このような心理的・社会的要因ともリンクしています。
3. 認知症リスクは2〜5倍に?
2017年の国際的な研究では、難聴が認知症の最大の修正可能リスク因子であると報告されました。中等度の難聴で約2倍、重度の難聴で5倍以上のリスクになるとされています。難聴と認知症の関係は医学的にも注目されており、世界中で研究が進められています。
どうすれば予防できる?早めの対策がカギ!
1. 補聴器の活用
聞こえに不安を感じたら、まず耳鼻科を受診し、必要に応じて補聴器の使用を検討しましょう。補聴器の使用は、脳への刺激を保ち、コミュニケーションを円滑にする助けになります。難聴と認知症の関係を考えるうえで、補聴器は有効な予防策の一つです。
2. 定期的な聴力検査
年齢とともに進行する難聴は、本人が気づきにくいこともあります。年に一度の健康診断の際に、聴力検査も加えることをおすすめします。早期発見・早期対策が難聴と認知症の関係の深刻化を防ぐ鍵となります。
3. 会話をあきらめない
聞こえづらくなっても、家族や周囲の人がゆっくり話す・目を見て話すなどの工夫をすることで、円滑な会話は可能です。積極的に会話を続けることは、脳を活性化させるうえでとても効果的です。
難聴を放置しないことが未来の自分を守る
難聴は「年のせい」として放置されがちですが、難聴と認知症の関係を理解すれば、今できることに取り組む価値が見えてきます。耳からの刺激を保ち、社会とのつながりを失わないことが、脳の健康を守るカギです。
「最近、テレビの音が大きいと言われる」「会話についていけない」と感じたら、無理せず早めに専門機関に相談してみましょう。あなたの聞こえと未来の健康、どちらも守るために。
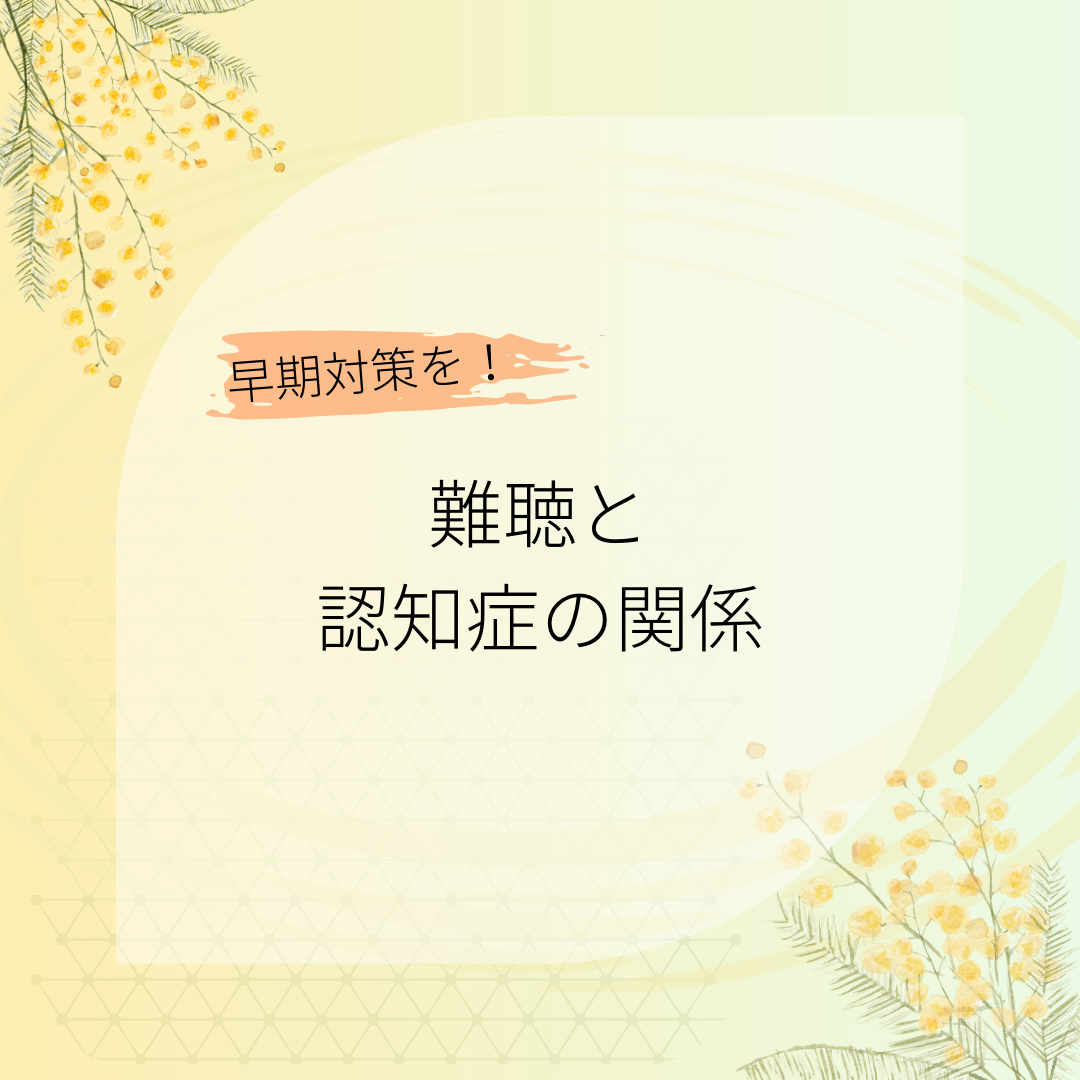

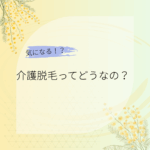
コメント